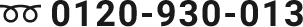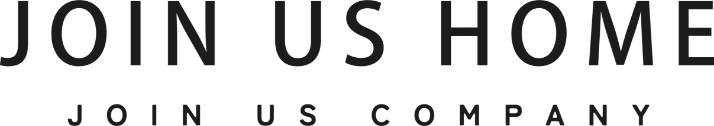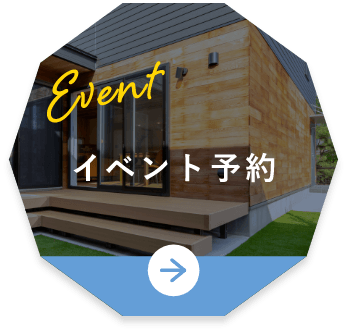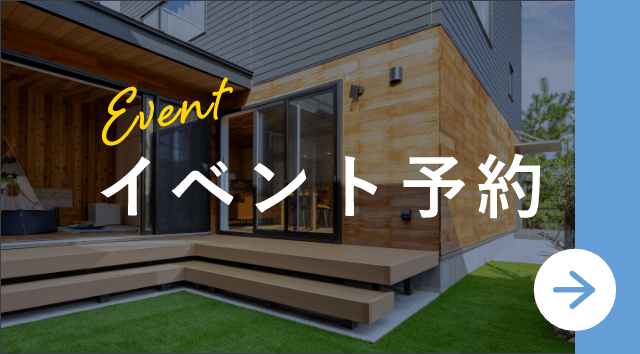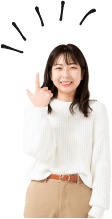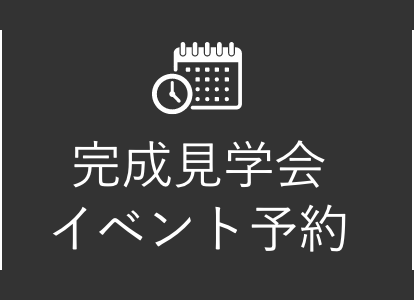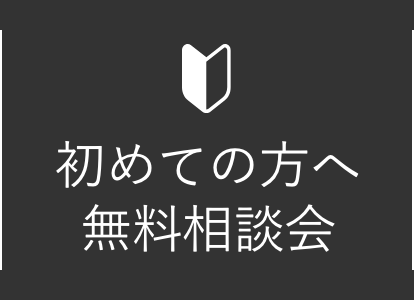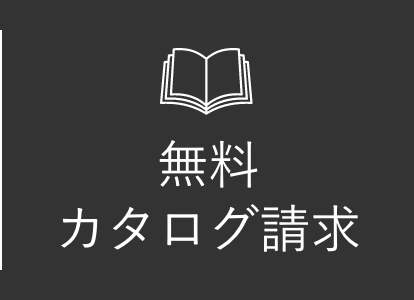-

2025/07/10
Q.子供連れで見学会などに参加できますか?
-

2025/07/08
“ずらし駅”で叶える理想のマイホームとは?
-

2025/07/01
平屋の魅力と後悔しない間取り~人気の1.5階建てについても解説
-

2025/06/24
グレーで統一された開放感あるインナーガレージ住宅~施工事例(I様邸宅)
-

2025/06/17
妥協しない素材選びとデザイン:間接照明・インテリア建材・造作洗面台で暮らしの質を高める
-

2025/06/10
家づくりの新しい風潮「デコ活」とは?~省エネ基準適合義務化との深い繋がり~
-

2025/06/05
Q.ジョイナスホームのモデルハウスはどこにありますか?
-

2025/06/05
Q.ジョイナスホームの施工エリアはどこですか?
-

2025/06/03
梅雨でも快適!湿気に強い家づくり
-

2025/05/27
ペットサロンのある愛犬と暮らす家~施工事例(N様邸宅)
-

2025/05/20
SNS映え抜群!ホテルライク・ラグジュアリーな家づくり:見た目のこだわり徹底解剖
-

2025/05/13
【2025年最新】スペースパフォーマンスを極める!コンパクトでも広々快適な間取りと収納術